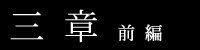
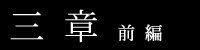
狼使いに連れられて啼が目的地に到着したのは、あれからすぐのことだった。遠くに見えていた筈の丘は目と鼻の先にあり、そこには啼の目指す大きな屋敷が構えている。
これが本来の距離感なのだろうか――啼はぼんやりと思った。自分が実際に歩き、感じたほどにこの庭園全体は広くないのかも知れない。
あの高い柵を越えた時点で、世界は一変した。
ここが闇の力によって制御されていることは啼も肌で感じた。土地の所有者が特別な力で空間を操作しているのであれば、様々な不可解なことにも説明もつく。正規の手続きを踏まない侵入者を翻弄する事も容易であろう。
大きな屋敷のまわりには一般人を立ち入らせないための柵があった。啼の頭より少し高い柵の向こう側には、横一列に植え込まれた薔薇と、目隠しのための植え込みがある。木の高さは柵と同じくらいだが、植え方が良いのか威圧感はなかった。
それはいかにも西洋の庭園らしい豪奢さがあった。こういった庭園も美しいと思う反面、些か人工的で、啼はいつも居心地の悪さを感じてしまう。
狼使いは柵沿いに、建物の裏手へと向かう。そこには使用人用の出入り口と思しき扉があり、内側には更に古めかしい木戸が構えていた。男は錠を外して木戸を開けると、狼を先に入れる。三頭の狼は軽い足取りで柵の中に消えた。啼も促されるままに入っていく。
外から見るよりも、ずっと大きな屋敷が構えていた。左右対称の造りをした白い屋敷は、ところどころに大理石が使われているようだ。しかし全体としては簡素で清楚な雰囲気があり、どこか女性的な印象を与えた。制作者が細部にまでこだわった結果なのだろうが、素直に美しいと啼は感じた。
屋敷の周囲も庭になっていて、遠くにテラスのようなものも見えるが、闇と雨ではっきりしたことは分からなかった。
白い屋敷の横には石造りの小屋と、使用人用の住居らしき建物があった。白い壁に黒い屋根、簡素ではあるが、そちらもどことなく優美な印象がある。
狼使いが扉を閉める間、啼は妙な感慨をもってその景色を見回していた。啼はここに初めて来たが、この場所を全く知らないわけではない。
突然、狼使いが声を発した。
それが外国語だろうとは判断出来たものの、啼には何と発音していたのかすら聞き取れなかった。あまりに聞き慣れない言語だった。
その言葉で、男は狼に指示を出したていた。振り返ると、狼たちは男の声に従い、扉が開いたままになっている石造りの小屋へと向かっていく。狼たちは入り口あたりで体を震わせ、水滴をまき散らしていた。
その姿を見届ける男の様子をまじまじと見ていて、啼は思わず
「詳しいことは知らないけど、君たちの種族は、もっと静かなところで暮らしているものだと思っていたよ」
言い切った瞬間、彼は後悔した。余計な詮索をするつもりはなかったのに、と。
男は、その後悔を見逃さなかったらしい。不愉快な顔をするでもなく、短く言った。
「私たちは、卿にとても大きな恩義がある」
不躾な行動を咎めるわけでもなく、男は静かに答える。
端的な言葉だったが、彼ら種族にとってそれがどれだけ重い意味を含むか、啼は理解していた。
「そうなのか。――ありがとう」
敬意を持って接したいと思う相手には、自分が感じたように素直に接する。それが啼だったが、その素直さは再び狼使いを少し驚かせた。だが、驚きはすぐに消えた。
何事もなかったかのように視線を戻し、「こっちだ」と言うと、闇の中を早足で歩き出した。
啼は屋敷の横にある、使用人用の建物へと連れて行かれた。
こちらは屋敷と異なり更に簡素な造りをしている。そして、外観だけでなく生活様式も完全に西洋のそれだった。
靴履きのまま家の中を歩き回る事に抵抗を感じる啼は、外国の様式にはいつも戸惑いを覚える。だが、この建物の中ではあまり違和感を感じなかった。庭園といい、すべてが別世界として設えられた空間だからかもしれない。
この古い建物が持つ独特の雰囲気、白い壁と焦茶色の床が、啼の気持ちを落ち着かせた。
土間で雨具を脱ぎ、その後案内された小部屋で、啼は屋敷の主に会う為の身支度をさせられた。
男が去るとほどなく、啼と同じか、少し若く見える華奢な女が現れた。黒髪、目は濃い灰色で銀でこそ無かったが、男とよく似た空気を纏っていた。彼らは同族なのだろう。
女はタオルと着替え、それと湯気の立ったをカップを持ってきた。白いシャツに黒のズボン。正装とは言わないまでも、屋敷の主にはそれなりの格好で会え、という事なのだろうが、啼はそれをやんわりと断った。女も無理強いはしなかったので、彼は装束姿のままでいた。
体を拭いて落ち着いたところで、女はカップを手渡してきた。受け取ってみると、それは暖めたミルクだった。蜂蜜の匂いがする。
啼は礼を述べ、改めて女を見た。これはたぶん、ずぶ濡れだった啼に対する、彼女の気遣いなのだろう。
「これ、子供の頃に飲んだよ」
そう言ってカップに口を付けた。懐かしい味がする。
啼の様子を見守っていた女は、小さく笑うと「あなたは、私たちからしたら、まだほんの子供だわ」と言った。
あやすような口調に、啼は思わず苦笑した。
「そう、そういうの――頭では分かっていても、いつもちょっと混乱する」
素直な感想だった。人とは時の流れが異なる種族に相対すると、啼はいつも不思議な感覚に陥る。特に、人と見分けのつかない種族に対しては。
彼らには独自の時間や世界があって、啼はそれを守るのも役目のひとつだと思っている。もちろん、お互いが干渉しすぎてはいけないのだが。
啼が女にカップを返したとき、部屋の扉が開いた。
狼使いが戻ってきたのだ。しかし、その印象は随分違っていた。
白いシャツに黒のズボン、先ほど啼が渡されたのと同じような服装。もちろん正装でないだろうが、その姿は執事や秘書といったものを連想させる。とても、あの狼たちを手懐けている庭園の番人には見えない。
女は狼使いと入れ違いで部屋を出ていったが、去り際に啼にそっと耳打ちした。
「あの方を、よろしくね」
あの方――。
啼は問いも答えもしなかったが、小さな笑顔で彼女を見送った。
そうして彼女が出ていった後、男は改めて啼の姿を見て、小さな溜息をついた。その様子に啼は一瞬だけ済まなさそうな顔をする。
「もしかして、君の主人が煩いのかな」
装束のままでは嫌がるだろうな、とは啼も考えた。本当に、どうでもいい事に煩い男だから。
狼使いはそれについて何も答えず、ただ「お前にはお前の流儀があるのだろう」と言って、啼を目で促した。
その建物は地下の細い通路で屋敷と繋がっていた。倉庫のような部屋へと続く薄暗い階段を上り、古めかしい道具が多く積み重なった部屋を出るとそこは、全くの異世界だった。
屋敷の内装はそのほとんどが白で構成されている。要所には金銀の塗装が施されているが、ささやかなものだった。壁に絵画の類はないが、大きな窓が目立った。また、所々に大きな鏡が設えられている。これらの大きな窓は額縁のような役目を果たし、鏡は光を反射するために設置されているように思えた。
そのほかの装飾的なものといえば、百合を象ったランプシェードと、壁に描かれる百合の紋章だろうか。周囲を薔薇に囲まれていたが、この屋敷のモチーフは百合らしい。
あとで分かったことだが、たしかにこの屋敷は百合がモチーフで、ある特定の種類の百合しか植えないのだという。ゆえに、それが咲かない時期は、白い薔薇などが代わりに植えられる――ということだった。
啼には様式など分からないが、非常に美しい建物だということは十分理解できた。屋敷の主人には良い印象を持っていない啼だが、趣味を少しだけ見直してしまった。
屋敷の中は、全体が微妙に明るく、雨の降る夜中だというのに灯りは必要がなかった。灯されたランプは決して強い光を放っているわけではないが、暖かい色をした光が充満している。自分の影もうっすらとしていて、微妙に平衡感覚が失われる。現実と夢の境界に対する感覚が。
中央の大きなエントランスを通り越し、奧へと進んでいく。啼が上がってきたのとちょうど逆あたりに位置する階段を昇り、二階の廊下に出る。いくつもの白い扉を通り越し、突き当たりの扉の前で狼使いは止まった。
「ここで待つようにとの指示だ」
扉を開け、中に入るよう指示した。啼は頷いて室内に入っていく。
四方の壁にかけられた百合のランプと全体を覆う灯りが、それまでの光以上に暖かく啼を迎えた。
部屋はやはり真っ白だが、ここには窓がなかった。また入り口の扉の向かい側にはもうひとつの扉があり、奥の部屋へ続いているようだった。
中央には、この屋敷の為に作られたらしい白いテーブルとソファが設えられている。だが啼はくつろぐ気にはなれなかった。
座る気はなかったが、なんとなくソファに近付いた時だった。
足音も、気配すらもなかったが、予感がした。入ってきた扉を振り返る。
と同時に、白い扉が大きく開かれ、金色の髪が目に飛び込んできた。
「君がここを訪れる日が来るとはね!」
はしゃいだような声。やけに楽しそうな様子で現れたのは、啼よりも長身の西洋人。彼は流暢にこの国の言葉を操った。
ゆったりした白いシャツに濃い紺色のズボンという出で立ちは部屋着であろうが、素材はいかにも高級そうに見える。
三十代後半くらいに見えるが、実際の年齢は分からない。知りたいとも思わなかった。
「久しぶりだね、啼。こんな夜分に、僕の館にようこそ」
啼の目の前でわざとらしく一礼して、軽薄そうな笑みを浮かべる。
屋敷の主。啼が秘密裏に会いに来た者――外鬼のザークシーズ卿。
彼こそが混血種の件で「人材」と「場所」を提供した人物だった。