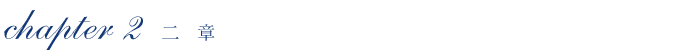車が止まる。雨音に向けていた意識を現実に引き戻すと、指先の冷たさに気が付いた。後部座席の啼は顔を上げる。
運転席の中年男は振り返り、「ここでいいのか?」と訊ねた。
都市部でハイヤーの運転手をしているこの男は、数字こそないが、弾きと呼ばれるしのびの一人だった。肆研隊に所属している。忍務のとき、啼はたびたびこの男の世話になっていた。
啼は軽く目をこすり、窓の外を見る。そこは、広大な庭園を南北に分ける一本道。止まったのはちょうど庭園の中央付近にあたり、木々の影が周囲を取り囲んでいた。
車は街灯の下に止まっていた。雨の降り続く真夜中ということもあるだろうが、周囲には人どころか、生き物の気配がほとんど感じられない。
「うん、ここでいい。—どうもありがとう」
街灯の灯りが啼のおぼろげな輪郭を浮き立たせる。そのぼんやりとした笑顔に、運転手は少し呆れたような口調で「暢気なもんだなあ」と呟いた。
「峰さん、おれがここに来たことは、ないしょだよ」
その言葉に運転手・峰は苦笑する。「お前さんには借りがあるからなァ…」溜息混じりに漏らし、姿勢を元に戻した。
「明後日には連絡するから。その時はよろしく」言いながら、啼は黒い雨具のフードを被ると、ドアに手を掛ける。
「俺は、お前さんの死体の回収だけはしねえからな」
前を向いたまま乱暴に言い放たれた言葉は、峰なりの気遣いだった。
これから啼が向かおうとしている場所を考えれば、不安にならないほうがおかしいだろう。
バックミラーに映る啼の目は、いつもと変わらなかった。啼の目は薄い黄土色をしていて、暗闇で光を受けるとまるで金色に見える。その目が笑った。
「たいした心配はないよ。まあ、ちょっと不愉快なだけかな」
啼は、本気で何も起こらないと信じているようだった。峰の心配を理解していないわけではないが、なにか確証があるのか、平然としている。億劫そうな雰囲気すら感じられて、峰は感心を通り越して些か呆れた。
「知らねぇぞ、俺ぁ」
「連絡するよ」
啼は車を降りる。扉が閉まると同時に、車は静かに走り去った。雨の中、遠ざかる車の音を聞きながら、啼は庭園へと向かっていった。
その庭園は都会の中心にあった。今でこそ道路によって南北に分割されているが、広大なの敷地は「森」と呼べる存在感を放っている。
そこはさる一族の私有地であった。何十年も前に、一族の邸宅して造られたものだが、庭園部分は十数年前より、特定の時間帯は一般に解放されていた。
ここは、都会のオアシスとして機能している。
公園は高く黒い柵で囲まれており、特に歴史的価値もある邸宅が建てられた北側は、入園の制限が細かく決められていた。制限を守らぬ者への罰則も厳しく定められている。
啼は、その北側の庭園に侵入しようとしていた。彼は立ち止まり、柵を見上げる。確かに高さはあるが、柵そのものに特別な仕掛けはなく、警報装置の類すら見当たらない。
——さしずめ、陰陽の世界を分ける境界ってとこかな。
啼はこの柵を結界のようなものだと感じた。この中には、外界と分かたれた世界があるのだ。
だとしても、躊躇する理由にはならない。啼は柵に寄り添うように傾いた楠の枝を使い、簡単に柵を越えた。
最初は木から木に移ろうかとも思ったが、先ほどより強くなった雨が啼の気配をかき消す。木から柵に移るとそのまま飛び降りた。音は降り続く雨に紛れた。
啼としては、音よりも、雨で足跡が残ることのほうが気になった。だが、正式な忍務でなく、何より本気で隠れて行動しているわけでもない。
まあ、なんとかなるだろう—啼はゴーグルを装着すると、すぐに歩き出した。
園の中には想像以上の世界が広がっていた。
そこはとても広かった。木々は鬱蒼と茂り、都会の一角だというのに、どこかの森に迷い込んだような感覚に陥る。
だが、この森は自然の森ではない。よく見れば、人の手によって美しく、細かく整備されていることが分かる。すべてのものは、住人にとって心地の良い形に整えられていた。
その予定調和はどこか不自然な気がした。啼は感心するよりも、その手の入り方に違和感を覚えていた。
こういうのも、箱庭と言うんだろうな。
木立を進みながら、啼は頭に入れた地図を確認していた。今いる地点よりも少し高台に目指す場所はあったが、そこにたどり着くにはもう暫くかかるだろう。近道かもしれないが、さすがに真ん中の平原を突っ切るわけにはいかない。
今進んでいる道はなだらかな下り坂で、下りきると池のほとりに出るのだが、そこを少しだけ迂回する必要があった。池のほとりには小さな小屋があり、夜は警備員が常駐しているということだった。手短に、穏便に済ませるためにも、出来るだけ接触は避けたい。
雨足が更に強まった。啼は池を少し迂回し、木々に隠れた脇の窪地をなるべく静かに進んだ。気配を消すだけでなく、細心の注意を払って。
来た時と同じように、どこにも生き物の気配は感じられなかった。
だが、それが大きな間違いだということに気付いたのは、丘に続くなだらかな斜面を上り始めた時だった。
木々の影。闇と雨。雨は音をかき消すだけではなく、他の者より優れている啼の嗅覚をも鈍らせていた。
——けもののにおいがする。
物音はまったくなく、気配も感じられなかった。草や雨のにおいに混ざって、かすかにけもののにおいがする。それも、かなり近い。
——まいったな。囲まれてる。
数はさほど多くないようだが、完全に周囲を囲まれているようだ。
それは啼らしくない失態だった。相手が気配を消す事に長けた闇のけものである事も理由のひとつだろうが、それ以上に、啼にはどうにも出来ない力がこの土地に働いている事が一番の理由のように思えた。
ここは、啼の暮らす場所ではなく、闇の支配する場所なのだ。
啼は脚を止めず、彼らに気付く前と同じ歩調で進む。
けものは警戒しているものの、襲ってくる様子はなかった。啼の出方を待っている、といった方が正しいだろう。侵入者に対して、敵意より戸惑いの方が強いように感じられた。
姿は見えないが、非常に統率の取れた動きをする彼らは、いわば「番犬」なのだろう。番犬なら操る者がいるはずだが、啼はその存在の片鱗すら確認することはできなかった。
……だが、なぜ、こんなところにいる?
もし、彼らが啼の想像通りのけものだとすれば、闇のけものの中でも崇高な存在と呼ばれる種族だ。こんな場所でなぜ、やつらを守るのだろうか。
予想が正しいか否かは別として、啼としてはすべてを、出来るだけ穏便に済ませたいと考えていた。もとより、ここではあまり隠れる気はない。戦闘さえ避けられれば、それでいいと思う。
しかし、この場で戦意が無いことを示しても、何の解決にもならないと分かっていた。なぜなら彼ら闇のものたちは、力無き者を認めようとはしないからだ。自然界の掟は、そのまま闇の掟でもあった。そのことを啼はよく識っている。
闇の中では、力無き者に慈悲はなく、弱い者は服従か死を選ぶ事となる。戦いを避けるためには、自らも強くあらねばならない。或いは、己の力を示し、相手に認めさせるしか方法はないだろう。
啼はルートを変えることにした。その方が厄介もすぐに済む。それに、目的地にも近いはずだ。
草原へと向かう。歩きながら啼は、雨具の内側の装備を確認した。ベルトの後ろにつけていた四角い革のケースを外し、左腕に装着する。
視界が徐々に開けてくる。視界の先には一面の芝生が見えた。なだらかな坂になっているが、見晴らしの良い、なにもない平地。意志を示すだけなら、そこのほうがいい。
啼を取り囲むけものの気配が一瞬消えた。啼は構わず森を出て歩き続ける。遮るものがなくなり、雨が容赦なく啼を打った。
ごうごうという雨音しか聞こえない。
急激ににおいが強まった。それは、けものが闘うときに発する特有のにおいだ。
次の瞬間、啼は身を翻した。
跳躍したそれは、頭上をかすめて啼の背後に着地した。そして、体勢を低く保ったまま啼を睨みつける。
「番犬というには立派すぎるね」
顔を上げて周囲を見ると、思わず呟いた。
それは、体長が一、五メートルはあろうかという狼だった。黒に銀の混ざったような毛並みは長く、目は銀色に輝いている。啼のはじめて見る狼だった。
彼の想像通りであり、想像以上だった。
闇のけものの中には、狼とそっくりなものたちがいる。彼らは神聖視されることが多く、特別に扱われた。実際闇のけものの中でも高い知能と精神性を持ち、ゆえに飼い慣らす事は非常に難しい。人間にとっては不可侵の存在とも言えた。
しかし、同じ闇の種族同士なら、それも可能なのかもしれない。
三頭の狼が、一定の距離をとりながら啼を取り囲んでいる。
目の前の狼が低いうなり声を上げた。右と背後に一頭ずつ。目の前にいる狼は他の二頭に比べて少し小柄だが、他に比べて威圧感があった。群れのリーダーだろう。
その狼が吠えた。と同時に、二頭の狼が飛びかかってきた。啼はそれを右に転がって避けるが、間髪入れずにリーダー格の狼が襲いかかってきた。啼は片膝をついたまま、左手に装着したケースから何かを引き出し、狼に向かって投げつけた。
至近距離での攻撃を避けきることが出来ず、狼は小さな悲鳴を上げて着地すると、唸りながら啼から離れた。だが、戦意を失ってはいない。低いうなり声を上げていた。
啼は立ち上がると、投げつけたものを手元に引き寄せる。それは平たい、紐のようなものだった。尖端には分銅がついている。紐はかなり長いらしく、小型のモーターで巻き取られる仕組みになっていた。
それは、鎖鎌と同じ発想で制作された、試作段階の武器であった。小型で携帯しやすいが、絶対的な攻撃力や殺傷能力に劣り、使いこなすにはかなりの修練が要った。扱いの難しい武器であったが、啼は好んでこれを使う。
先ほどの攻撃に虚を突かれたようだったが、狼たちはまだ武器がどんなものか理解していなかった。再び二頭が啼めがけて突進してきたが、それをすり抜けるように避ける。避けた瞬間、少し離れたところで構えていたリーダー格の狼に向かって再び攻撃を仕掛けた。
狼は飛び退いて攻撃をかわす仕草を見せたが、それは出来なかった。紐が胴体に巻き付いた瞬間、啼は手を引いた。どうと大きな音を立てて、狼は地に落ちた。
残りの二頭はうなり声を上げたが、攻撃を仕掛ける様子はなかった。彼らにとって、指示以上の事態が起こっているのかも知れない。
啼は右手で紐をたぐりながら、周囲を見回す。どこかにこの狼たちを操る狼使いがいるはずだ。
「これ以上、戦う気はない」
立ち上がり、大声で言った。
「おれはかくれ郷の者だ」
啼は再び周囲を見回した。
すると、雨音に紛れて、静かな足音が聞こえた。気配を消すことを辞めたのだろう。足音は森のほうから響いてくる。
狼たちは唸るのを辞めた。地に伏した狼も立ち上がり、彼らの主人を待っているようだった。
狼の視線を辿り、啼は振り返る。そこには、雨に濡れた一人の男がいた。黒い衣に身を包んだ男は、狼たちと同じ銀の目を持っていた。
二頭の狼は現れた男が傍に来ると少しまとわりついてから、その背後にまわった。
男は啼が倒した狼の傍らに跪くと、巻き付いた紐を外す。自由になった狼は大きく体を震わせてから、嬉しそうに男を仰ぎ見た。
狼に怪我はないようだ。啼はほっとして、改めて男を観察する。
身長は啼よりも少し低いが、体つきはずっと逞しい。啼より少し年上にしか見えないが、年老いた戦士のような存在感がある。実際の年齢は分からないが、啼よりずっと長く生きていることは確かだろう。
男は屈んだまま、手にした啼の武器を眺めていたが、立ち上がって尖端を啼に差し出す。啼はそれを黙って受け取ると、武器を左腕のケースに格納した。
「やはり、郷の者か。面白いものを使うな」
短い黒髪が雨に濡れ、銀に光る。この国の言葉を流暢に使っているが、風貌から国の者ではないことが分かる。しかし、男はどの国の者にも見えなかった。
男は立ち上がると啼を見つめた。狼は彼の背後で耳を澄ましている。
雨は容赦なく降り続いていたが、啼はゴーグルを外し、フードをとった。
「七九番、伍隊の啼だ」
再びフードを被り、続けた。
「おれはある事情から、君たちの主・ザークシーズ卿に会いに来た」
「こんな時間に一人で、なぜ」
間髪入れず、男は訊ねた。大きくはない声が、真っ直ぐに耳に届く。
「それは、おれの都合だ。でも、そのせいで君たちの手を煩わせてしまった。申し訳ない」
その謝罪は些か意外だったらしく、男は少し目を見開いた。構わずに啼は続ける。
「おれは彼とかつて、ある約束を交わした。……面倒ついでで申し訳ないけど、内密に取り次いでくれないかな」
そして、男の反応を待った。
男はしばらく啼の顔を見つめていた。啼も男を見返す。嘘はついていない。真実を述べただけだ、と。
「その言葉に偽りはないな」
男は、静かに問う。銀の目が発光しているように見えた。
「ない」
啼は強く頷いた。
「誓えるな」
「ああ」
短い問答であったが、確信するものがあったのだろう。男は決断した。
「すぐ会えるかはわからんが、約束は守られなければならない。お前の望みを叶えてやろう」
「ありがとう」
啼は雨の中、狼に囲まれて男の後をついていった。